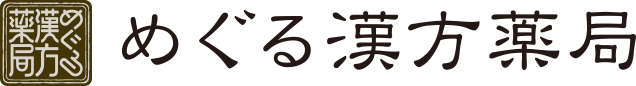名古屋市守山区小幡太田16-7 営業時間 10:00~19:00(土 18:00迄) 定休日 水・日・祝 TEL:052-792-7225
めぐるコラム
暑いのに冷えて夏バテ
先日大ヒット中の【鬼退治】のアニメ映画を観に行きました。最初からずっと観ていますが、毎回映像美と内容に圧倒されます。
ただ、今回も出ました。『病気のお父さんのために薬が必要なのに高くて買えない。それで盗みをやってしまう』くだり...。
今回のアニメ映画の舞台は確か大正時代ですが、さまざまなドラマなどの昭和初期や明治、江戸時代の設定でしばしば出てくる『薬が必要なのに高くて買えない』『病気のおとう(おかあ)のために滋養のつく食べ物が無いといけないのに買えない』くだり...。
薬も滋養のつく食べ物も一部貴族などお金持ちしか手に入らない時代が長く、現在のように薬も食べ物も手に入れようと思えば割と簡単に誰でも手に入るのはここ30~40年くらいの事なのでしょうか。
ここでいう『薬』はほとんど漢方薬だったと考えます。『漢方』という言葉は江戸時代から使われるようになった日本独自の呼び方です。
食養生の考え方も中国は古くからの有名な書物があり、3世紀末から4世紀にかけて日本に伝えられたとされますが、一般に広まるのは江戸時代です。幕府の学問保護の影響で急速な発展を遂げました。本草学者・貝原益軒の【大和本草】【養生訓】や、医師・名古屋玄医の【閲甫食物本草】など有名な『食養』関連の書物が著されたのもこの頃です。
江戸時代の後半には西洋医学の導入とともに『食養』の考え方は衰退し、西洋医学・西洋栄養学を重視する時代に入っていきました。
近年になって食の欧米化により生活習慣病を患う人が増加したため、日本の伝統的な食生活が見直されています。
江戸時代から昭和初期あたりまでの庶民の『滋養のつく食べ物』とは何だったのでしょう?
うなぎ・牡蠣・山芋・豆腐・卵などでしょうか?
江戸時代あたりの庶民は漬物や汁物少しに、ご飯(米)を山盛り食べる食事スタイルだったようです。
現代と違って精米しすぎていないので、胚芽や米ぬかからビタミンやミネラル、食物繊維を補っていたようです。それで飛脚などは何十㎞も走っていたというのですから恐るべし米パワーですね。
そういえば【鬼退治】アニメの中でもしばしば出てくる食事シーンでは主人公を始め、皆が大きな『おにぎり』をたくさんに漬物、お茶などをすごい勢いで食べて、身体を苛酷に鍛えたり戦ったりしています。
普段は米パワーで動けているのでしょうが、病気にかかるとミネラルやビタミン・たんぱく質などが全然足らない状態になるのでしょうね。
現代では薬も漢方薬も栄養の摂れる食べ物も、庶民でも割と簡単に手に入れることができます。
ただ、それだけでは解決しない病気も増えているので、いつの時代も病気に悩まない世の中は来ないのかもしれませんね。
例年はお盆を過ぎれば朝晩は涼しく過ごしやすくなって『もう秋がくるな...寂しいな』などと感じていたものですが、今年はまだまだ湿気のまとわりつく嫌な暑さが朝から晩まで続くばかり。
1日中冷房の効いた部屋にいないと日常生活もままなりません。
仕方のないことですが、それで今度は冷えて体調を崩したり、夏バテの症状を訴える方がお客様にも増えています。
『冷やしすぎない』状態を保つのは今のような気候とエアコンの使い方では難しいかもしれませんね。
このような冷えにはやはり食べ物・飲み物から温かいものを摂り入れる・お風呂はシャワーだけで済まさず湯舟に浸かるなどが有効です。
それでも不調が続く時は漢方をお試しになっても良いかと思います。めぐる漢方薬局にご相談ください。
ただ、今回も出ました。『病気のお父さんのために薬が必要なのに高くて買えない。それで盗みをやってしまう』くだり...。
今回のアニメ映画の舞台は確か大正時代ですが、さまざまなドラマなどの昭和初期や明治、江戸時代の設定でしばしば出てくる『薬が必要なのに高くて買えない』『病気のおとう(おかあ)のために滋養のつく食べ物が無いといけないのに買えない』くだり...。
薬も滋養のつく食べ物も一部貴族などお金持ちしか手に入らない時代が長く、現在のように薬も食べ物も手に入れようと思えば割と簡単に誰でも手に入るのはここ30~40年くらいの事なのでしょうか。
ここでいう『薬』はほとんど漢方薬だったと考えます。『漢方』という言葉は江戸時代から使われるようになった日本独自の呼び方です。
食養生の考え方も中国は古くからの有名な書物があり、3世紀末から4世紀にかけて日本に伝えられたとされますが、一般に広まるのは江戸時代です。幕府の学問保護の影響で急速な発展を遂げました。本草学者・貝原益軒の【大和本草】【養生訓】や、医師・名古屋玄医の【閲甫食物本草】など有名な『食養』関連の書物が著されたのもこの頃です。
江戸時代の後半には西洋医学の導入とともに『食養』の考え方は衰退し、西洋医学・西洋栄養学を重視する時代に入っていきました。
近年になって食の欧米化により生活習慣病を患う人が増加したため、日本の伝統的な食生活が見直されています。
江戸時代から昭和初期あたりまでの庶民の『滋養のつく食べ物』とは何だったのでしょう?
うなぎ・牡蠣・山芋・豆腐・卵などでしょうか?
江戸時代あたりの庶民は漬物や汁物少しに、ご飯(米)を山盛り食べる食事スタイルだったようです。
現代と違って精米しすぎていないので、胚芽や米ぬかからビタミンやミネラル、食物繊維を補っていたようです。それで飛脚などは何十㎞も走っていたというのですから恐るべし米パワーですね。
そういえば【鬼退治】アニメの中でもしばしば出てくる食事シーンでは主人公を始め、皆が大きな『おにぎり』をたくさんに漬物、お茶などをすごい勢いで食べて、身体を苛酷に鍛えたり戦ったりしています。
普段は米パワーで動けているのでしょうが、病気にかかるとミネラルやビタミン・たんぱく質などが全然足らない状態になるのでしょうね。
現代では薬も漢方薬も栄養の摂れる食べ物も、庶民でも割と簡単に手に入れることができます。
ただ、それだけでは解決しない病気も増えているので、いつの時代も病気に悩まない世の中は来ないのかもしれませんね。
例年はお盆を過ぎれば朝晩は涼しく過ごしやすくなって『もう秋がくるな...寂しいな』などと感じていたものですが、今年はまだまだ湿気のまとわりつく嫌な暑さが朝から晩まで続くばかり。
1日中冷房の効いた部屋にいないと日常生活もままなりません。
仕方のないことですが、それで今度は冷えて体調を崩したり、夏バテの症状を訴える方がお客様にも増えています。
『冷やしすぎない』状態を保つのは今のような気候とエアコンの使い方では難しいかもしれませんね。
このような冷えにはやはり食べ物・飲み物から温かいものを摂り入れる・お風呂はシャワーだけで済まさず湯舟に浸かるなどが有効です。
それでも不調が続く時は漢方をお試しになっても良いかと思います。めぐる漢方薬局にご相談ください。